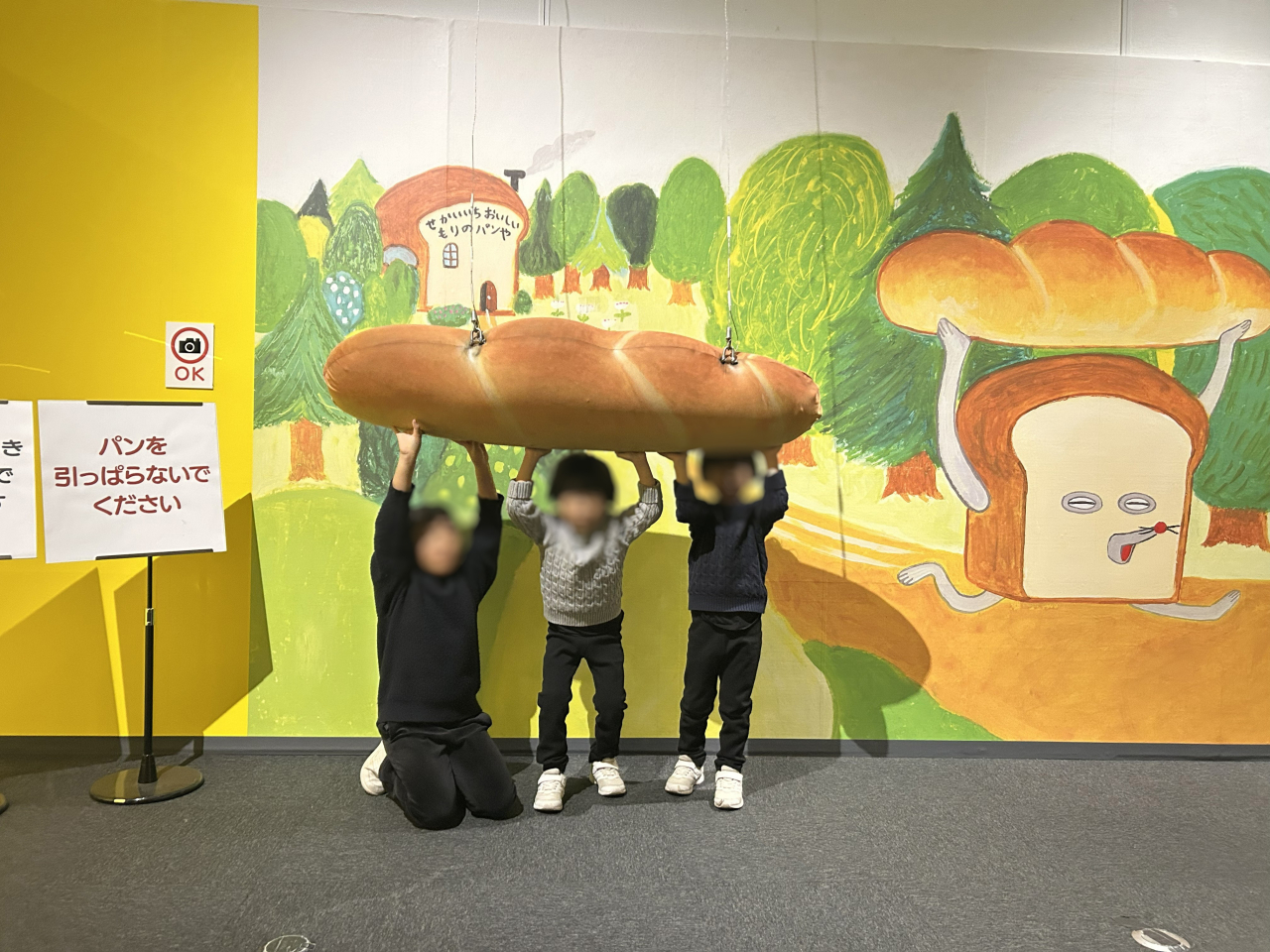スタッフブログ
2026.02.25
ガナッシュクッキー
こんにちは。井上です。
倉敷へ奥田民生さんのライブに行く予定にしていましたが、ご本人さんの体調不良により延期になりました。
だいぶ回復されているということですが、大事をとって計4公演延期となりました。
高校のときから追いかけてきた民生さんは、いまや60歳。
心配ですが、また元気な姿をライブで見せてもらえたらな、と思っています☺
さて、私はバレンタインデーに、ガナッシュクッキーを作りました。
大きめの丸いクッキーにくぼみを作り、そこへガナッシュチョコを流し込んで、板チョコやクマのチョコをトッピングしました。
まず、溶かしたチョコを、それぞれの型に流し入れ、冷蔵庫で冷やします。
ここで使用した型は、クマの型と、小さな板チョコの型で、両方ともシリコン製です。


次に、クッキー生地を作ります。
無塩バターをレンジで溶かし、砂糖、卵などを入れて混ぜ、粉類を入れ切るようにゴムベラで混ぜて、冷蔵庫で休ませます。
休ませた生地を等分にし、丸く成形したら軽く押して表面を平らにします。

オーブンで15分前後焼いた後、さじを使ってクッキー生地の中心にくぼみを作ります。

くぼみに流し込むガナッシュを作ります。
刻んだ板チョコと生クリームをあたため、溶かし、くぼみに絞り入れます。
そこへ、ミニ板チョコやクマチョコをトッピングし、冷蔵庫で冷やして完成です。


ピンクのクッキーは、いちごパウダー入りで甘く、ミニ板チョコは、ピンクチョコ(板チョコ)を使いました。
ガナッシュが温かいうちに板チョコを置いたため、少し溶けてしまいました。

また、茶色いクッキーは、少し苦みのあるココア味で、ガナッシュはピンクチョコを使用。
クマがガナッシュ内でぷかぷか浮かんでいる様子は、とても可愛く、愛らしいですね🐻

今回は、作業途中の写真がほぼなく、型や道具の紹介が主でした。
チョコレートは扱いが難しいですが、楽しく作業でき、なんとか上手く出来て良かったです♬
- 1 / 118
- »